服部雄一郎の過怠・序
伊賀の里には、そこで生きる者たちが大人になる為に通らねばならない関門がある。それは、この里が隠里となった古より連綿と続く通過儀礼である。
天正九年(一五八一年)、第二次天正伊賀の乱を生き延びた伊賀忍者たちの一部は、秘密の抜け穴を通ってかくれ谷へ逃れ、外部へ繋がる道を閉ざして里を作った。以後四〇〇年にも及ぶ長い時の中、彼らだけで子孫を残していくために、それは必要不可欠な教えだった。
その教えとは、男が妻を、女が夫を迎え、子を産み育てるために必要な知識、「男女の心身とその和合の教え」である。
隠里の男子たちは、数え十五の年に男衆の集まりと呼ばれる集会に参加し、同性の年長者を師に迎えて自身と異性の心身についての教えを受ける。同じように女子はくノ一衆の集まりと呼ばれる集会で、数え十三の年に自身の、十六の年に異性についての教えを受ける。男衆の集まりを経た男子は、その後それぞれが成人女性に導かれて男となり、十六のくノ一衆の集まりを経た女子は床入儀を行い、ようやく一人前の男女として婚姻を許されるのだった。
床入儀とは、十六のくノ一衆の集まりを終えた娘を成人男性が数日預かり、寝食を共にしながら夜の営みを教え、大人の女に導く儀式のことである。それを担う成人男性のことを床親、契約を結んだ娘を床娘と呼び、二人は擬似夫婦関係となる。通常、床親になるのは村の権力者や神職者、親戚筋の既婚男性だが、娘側から相手を指定することも出来、男が未婚の場合は床親からそのまま夫となることも多かった。
こうして、伊賀隠里では親から子へ、子から孫へ、忍びの術と生きる教えが受け継がれ、外の世界とは全く異なる時間が、ただゆっくりと流れていった。
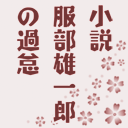
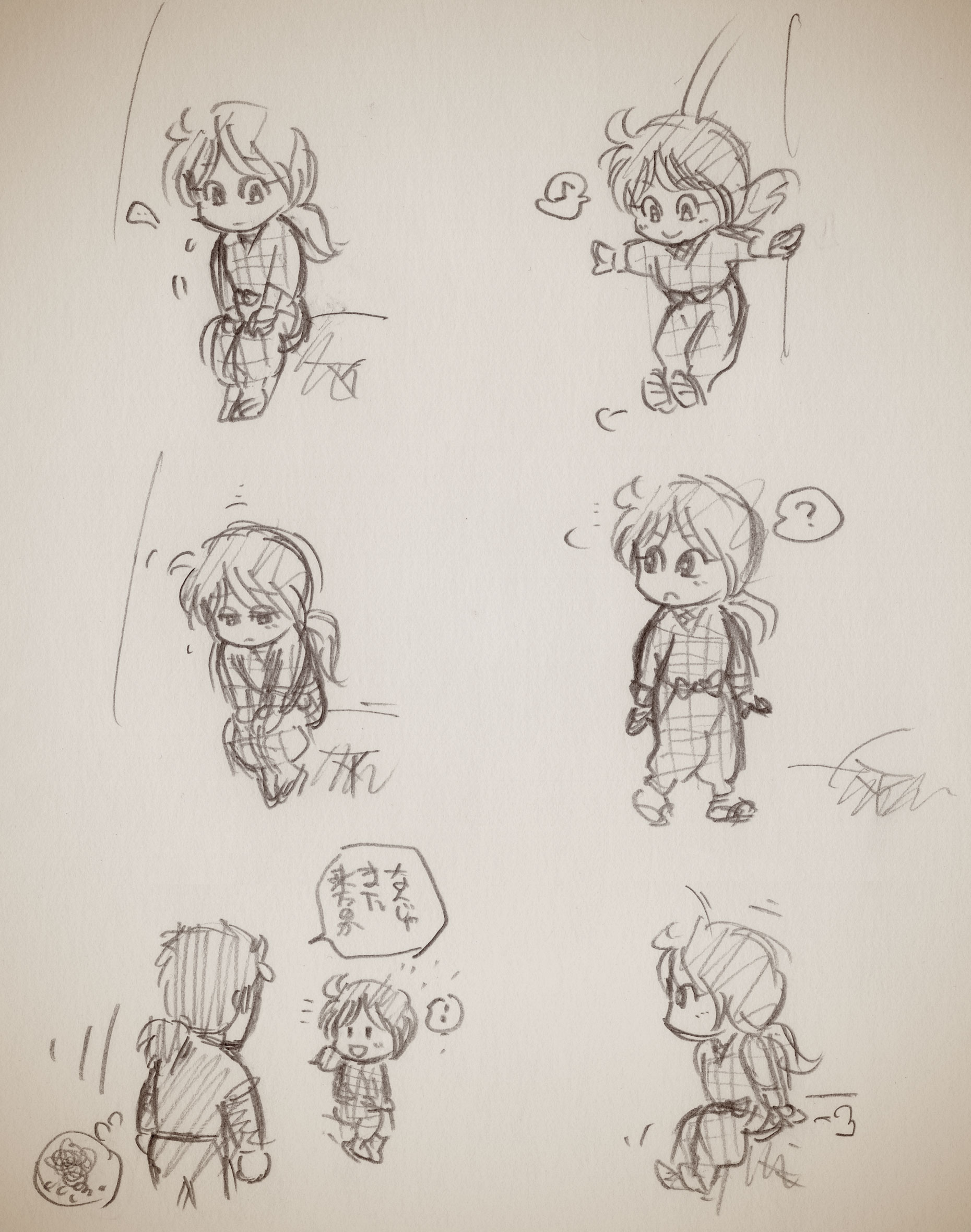

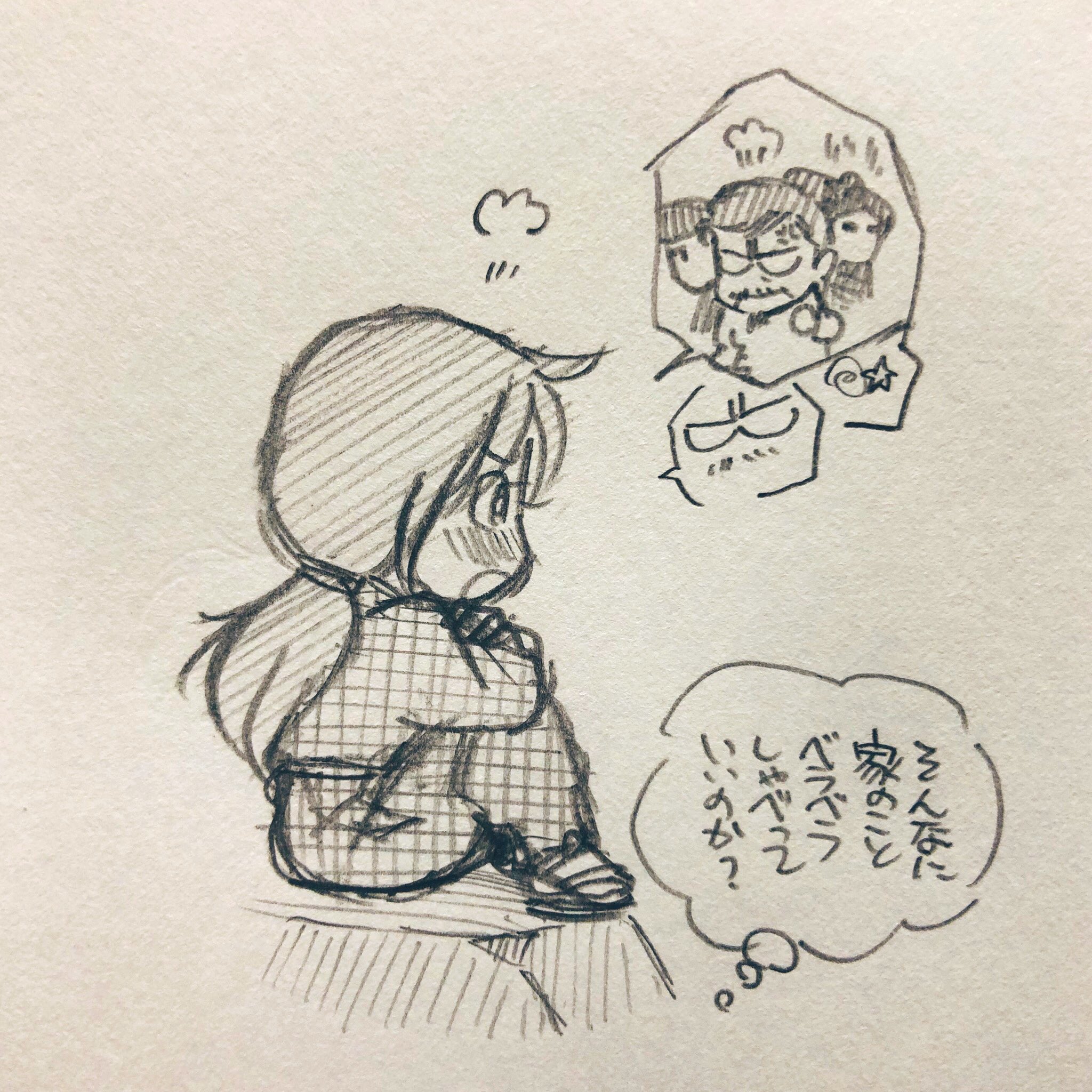
「私の床親になってください」
桃の花もちらほらと咲き始めたある日、服部雄一郎は、新堂家のひとり娘、穂高から床親になってほしいと申し込まれた。
雄一郎は、即座にその申入れを断った。雄一郎は今年で数え二十五歳である。十八で男になった日から既に七年もの歳月が経つが、それからただ一人の女も抱いていない。手ほどきをしてくれた女からは、男として申し分なしとお墨付きをもらってはいたが、他人と、まして女と深く関わりあうのは御免だと、雄一郎は思っていた。
頑として首を縦に振らない雄一郎を、穂高は請い、願い、訴え、挑発し、知りうる限りの言葉を尽くして説き伏せると、強引に床親を引き受けさせた。それは思い詰めに詰め、悩みに悩んだ果てに穂高がとった、一世一代の賭けだった。
新堂家は、かつて伊賀忍術名人十一人の一人と言われた新堂小太郎を祖に持つ古い家柄である。穂高の父親の新堂少太郎はこの祖先を誰よりも誇りに思い、何より家名を重んじる男だった。そんな少太郎にとって、雄一郎は、服部とは名ばかりの落ちこぼれで、村の者にも『外れの雄蔵』などと渾名される半端者でしかなかった。
そんなところに我が新堂家の娘を預けるのはまかりならんと気色ばむ父親に、穂高は雄一郎からの承諾は得ているのに、今更こちらから翻意するなど、我が家のみならず服部家にも恥をかかせることになるが、それでも良いのかなどと脅しすかして、渋々許諾を得たのだった。
穂高は以前から、密かに雄一郎に想いを寄せていた。村に属せず、村外れの「ひとつ山」に独りで暮らす雄一郎は、村人からは忍びとしても男としても役立たずと揶揄されていたが、自分の知っている雄一郎は、そんな無能者だとはとても思えなかった。だが周囲を説得している時間がなかった。両親がいつ自分を床娘に出すか分からない、だから決死の覚悟で床親になってほしいと申し込んだのだった。そしてその願いは叶えられた。
ところが、雄一郎は穂高が思っていた以上に世俗に疎かった。未婚の娘からの床親指名が婚姻の申し込みに等しいことを知らぬまま床入儀を終えると、雄一郎は訪れた新堂家の使いの者に穂高を託して家に帰してしまった。傷ついた穂高は、途中で使いの者をまいて姿をくらました。ひとり帰った使いの者から事の顛末を聞いた少太郎は、娘と家を侮辱されたと激怒し、雄一郎を討ち果たすべく、妻の弓を伴って、ひとつ山に向かった。
一方、雄一郎は友人の東海林輝之から床親指名の真意を聞かされ凍りついた。取り返しのつかない過ちを犯したことを知った雄一郎は、命をもって償うしかないと切腹しようとするが、そこに殺気立った穂高の両親が現れ、死ぬ前に娘を返せと刃を向けた。家に帰ったとばかり思っていた穂高が失踪したと聞いて、雄一郎は自宅を隅々まで探すが穂高は見つからない。
その時、穂高と初めて出会った日のことが雄一郎の脳裏に浮かんだ。雄一郎は駆り立てられるように走り出した。